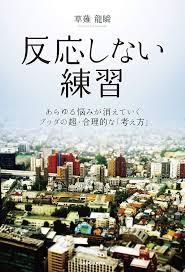私の周りの小学生のスマホ事情
私の周囲は、田舎ということもあり小学生で自分のスマホを与えられている人は多くない印象。クラスに3人から5人ぐらいかな?30人クラスだとすると1割から2割。
私は、与えない派。
「大切な事(物)を大切にできない未熟者には与える意味無いな。」と思ってマス。
我が子が精神的に成熟していないから↑のように感じているのであって、分別の付く小学生なら与えて良いと思ってはいます。
でも、最高学年の6年生だとしても、やっぱり、楽しいもの・楽なもの・興味のあるものに時間を使ってしまうのはあたりまえで、勉強や習い事やお手伝いや睡眠の時間を削ってスマホを触ってしまうわけです。
高校生になって、スマホに依存して、親の忠告を無視して堕落してしまうのは、自己責任7割かな、、、と。
でも、小学生にスマホ与えて「依存するな!」「勉強しろ!」と言われても、赤ちゃんに、目の前のお母さんが優しく手招きしているのに「甘えるな!!」と言っているのと同じぐらい、無理な事を強要していると、私は思います。
小学生にスマホを与えるって、赤ちゃんにとってもお母さんに甘えるのと同じぐらい、強烈な影響があるのではないかと。だれかそういう論文しりませんか?
リスクは犯罪だけではない
スマートデバイスの低年齢化による問題点は「ネット上での出会いによる犯罪」が挙げられるけど、それは本当の意味で親が目を光らせていれば防げる可能性も高いように思う。
監視を怠ったり、「自分の子は慎重なタイプだから大丈夫。」「困ったときには何でも相談してくれる子だから」と、我が子を過信している親は要注意。「うちの子に限って」なんて甘い考えは、捨て去って、過度なほど確かめて、ウザがられるほど疑って、プライバシーなんて無視して監視することができないなら、幼い我が子にスマホやタブレットなんか持たせない方がいいのではないでしょうか。
警戒すべきはわかりやすい犯罪だけではないからです。
幼さゆえに繰り広げられる友達同士のキツイ言葉の応酬や、心無いように感じられる一言。こういった文字の積み重ねで心を疲弊してしまう子も多くいると思うのです。大人からしたらさほど違和感を感じない一言でも、子供の世界では残酷な言葉の可能性もあります。そういう文字に気づいてフォローできる能力が親に無いのなら、子供にスマホを持たせるのは無責任というものではないでしょうか。
TikTokやインスタなど、見て楽しむだけのアプリに思えても、DMを使ってのやり取りの中に、我が子を傷つける文字が潜んでいる場合もあります。すべてのアプリを親が把握して、「誰かに傷つけられていないか」「誰かを傷つけていないか」「犯罪に巻き込まれていないか」「犯罪者になっていないか」を正視眼で見定めることができる親がどれだけいるでしょうか。
持たせない勇気
「周りの子はみんなスマホもってるよ」と言われると、ついつい「そろそろうちの子も??」という気持ちになるのは親心。スマホを持ってないと「仲間外れにされちゃうかも、、、?」と心配にもなりますよね。
でも、「スマホを持ってない」という理由で、疎遠になる友達なら、疎遠になったほうが良いのでは。
逆を言えば「スマホ持ってるから友達だよね」って(笑)。そんな友達いなくても大丈夫!
自分で大切なものを理解して、楽なほうに流されずにやるべきことに集中できる精神力が養われるまで、親が悪者になって、我が子からスマホを遠ざけて、精神力が養われてからスマホを手にしても、「遅すぎた!!!!」と、後悔する日なんて来ないんじゃないですかね?
早くからスマホ依存症になってしまっている我が子と、スマホを持っていないゆえに、他になるべきことを見つけ趣味や習い事や勉強に打ち込んでいる隣の子を見比べて「うちの子スマホばっかりで大丈夫??」と不安になる日は、結構な確率で来そうですよね。
ほな!